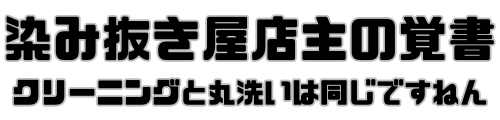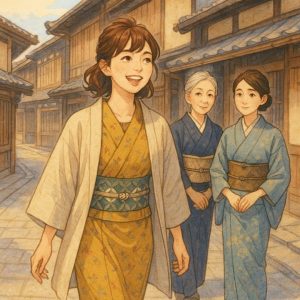着物の種類と格 その歴史
着物の種類と格、歴史、現代の状況・課題、そして未来へ繋ぐには?
第一章:着物の始まりと現代までの歴史と変遷
着物は、日本の長い歴史の中で独自の進化を遂げてきた衣服であり、その変遷は日本の社会、文化、技術の発展を色濃く反映しています。古代の身を守るだけの簡素な装いから、時代ごとの美意識や実用性に応じて多様な形態へと変化し、現代に至るまでその伝統は受け継がれてきました。
1.1 着物の起源と古代の衣服(縄文・弥生・古墳時代)
着物の歴史は日本の古代の時代にまで遡り、その原型は狩猟採集社会の衣服に見られます。縄文時代には、衣服の主な目的は防寒と肉体保護であり、狩猟で得た獣の皮や羽毛、木の皮などを身体に巻き付けた簡素なものであったとされていますが、この時代には装飾性はほとんど見られませんでした。しかし、後期には農業の発展に伴い、カラムシ(苧麻)や麻などの植物繊維から糸を紡ぎ、今も衣類を作るのには欠くことの出来ない織りの製法の原点で、織物が作られるようになっていきました。
弥生時代に入ると、中国の歴史書「魏志倭人伝」の記述から、女性は布の中央に穴を開けて頭を通す袖なしの「貫頭衣(かんとうい)」を、男性は一枚の布を巻き付けた「巻布衣(かんぷい)」を着用していたことが知られていますが、この時代には、身分の高い人々は絹の衣服を身につけ、原始的な機織りや紫草、藍などの植物染料による染色も行われていました。この時期から、衣服が単なる生存のための道具から、社会的な意味合いを持つものへと変化し始めたことが観察されます。
古墳時代には、大陸との交流が盛んになり、中国の影響を受けて衣服の形態が大きく変化しました。女性は「筒袖(つつそで)」の上衣にスカート状の「衣裳(きぬも)」を、男性は筒袖の上衣にズボン状の「衣褌(きぬばかま)」を着用していたとされており、この時代の特徴として、前合わせが現代の着物の装いとは逆の「左前」であったことが埴輪から確認されています。また、養蚕が盛んになり、絹織物が増加したこともこの時代の特筆すべき点と言えるでしょう。
衣服の進化は、その時代の技術発展(織物、染色、養蚕)だけでなく、社会構造(身分制度)や国際交流(大陸文化の伝来)と密接に連動しており、文化的な産物が孤立して発展するのではなく、常に外部環境との相互作用の中で形作られるという普遍的な現象が既にこの時期に見られるのはとても興味深いと言えます。
1.2 飛鳥・奈良時代の中国文化の影響と「右前」の確立
飛鳥・奈良時代は、遣隋使や遣唐使を通じた中国文化の積極的な導入により、日本の衣服文化に大きな転換期をもたらした時期になります。中国の「漢服」が参考にされ、袖が大きくゆったりとしたデザインへと進化し、衣服が単なる防寒具ではなく、身分や権力を示す重要な役割を果たすようになったと考えられています。
聖徳太子による冠位十二階の制定や、奈良時代の三公服(礼服、朝服、制服)の制定により、衣服は明確な身分制度と結びつき、支配階級は高級な絹織物を、労働階級の庶民は麻を使用するという階層が確立されました。この時期に「右前の衿あわせ」が法律によって定められ、それまでの「左前」から現在の前合わせに改められたことは、単なる着付けのルール変更に留まらない。これは、国家が国民を統治し、社会秩序を維持するための強力なツールとして衣服を認識し、文化的な要素を政治的・社会的な意図を持って標準化しようとした試みであると言えるでしょう。この「右前」の確立は、中国文化の受容と日本独自の文化形成の過渡期における、国家による文化的な自立と統一の試みと解釈でき、後の時代に着物が日本の国民服として定着する基盤を最初に築いた出来事と言えます。
1.3 平安時代の貴族文化と「直衣」「小袖」の登場
平安時代は、貴族文化が花開き、現在の着物の原型が形成された重要な時期となります。この時代には、現在の着物の原型とも言える「直衣(のうし)」が誕生し、日本の貴族社会で重要な役割を果たすようになっていきました。直衣は「束帯(そくたい)」を簡略化した平服という位置づけであり、天皇の許可があれば、朝廷への参内にも用いられました。貴族たちは、重ねの色目や季節ごとの文様でセンスを競い、美意識が衣服に色濃く反映されました。また、衵(あこめ)を長く仕立て、直衣の下から少し見せる着方も豪華で美しいとされていました。
一方で、袖口の小さい「小袖(こそで)」は、平安時代の公家装束の「下着」のような役割を担っていました。しかし、オフィシャルな場以外では、楽な小袖で過ごすことが次第に多くなっていったとされています。庶民にとっては、小袖は既に日常の衣服、つまりは現代で言うところのいわゆる普段着として定着していました。この時代には、絹織物を重ね着する「有職装束」が発展し、その一番下に着られたのが小袖でありました。貴族の「下着」であった小袖が、非公式な場では「表着」として着用されるようになった事実は、衣服のフォーマリティが状況に応じて柔軟に変化し始めたことを示しています。これは、実用性や快適性が、厳格な階級制度や儀礼性の中でも徐々に重視されるようになった兆候であり、後の時代に小袖が庶民から貴族・武士まで広く普及する下地となりました。
1.4 鎌倉・室町時代の武士文化と「小袖」の表着化
鎌倉時代以降、武士の台頭は着物文化に大きな変化をもたらし、「小袖」が広く普及する契機となりました。武士の台頭とともに、衣服はより実用的で動きやすいものへと変化していったのです。
鎌倉時代には、小袖が下着ではなく表着として着られるようになり、身分や貧富に問わず広く普及しました。室町時代には、庶民の間で着られていた小袖を武士や公家が着ることが認められ、表着(うわぎ)として定着しました。これは、社会の支配層が交代することで、ファッションの主流が変化し、より機能的でシンプルなスタイルが受け入れられるようになったことを示しています。武士階級が実用性を重視した結果、庶民の日常着であった小袖が上流階級にも浸透し、最終的に表着として定着したと言えるでしょう。
この時期には、小袖に様々な模様が付けられるようになり、多種多様な染色の技術が飛躍的に発展しました。庶民は重ね着ができないため、持っている小袖を染めて模様を付けることでおしゃれを楽しんでいました。貴族や武士の女性も、重ね着だけでなく小袖の色や模様を楽しむようになり、小袖の表着化と染色の技術の発達・発展は、単なる衣服の進化ではなく、庶民の購買力向上と美意識の多様化、そしてそれに応える職人技術の進歩が相互に作用した結果であり、後の江戸時代の「着物文化の黄金期」の多様なデザインや柄の基礎が築かれたと言えます。
1.5 江戸時代の着物文化の黄金期と多様な発展
江戸時代は、平和な時代背景と商業・文化の発展により、着物文化が最も栄えた時期とされています。この時代には、着物は階級や季節、流行に応じて様々なスタイルや柄が生み出され、歴史的には「着物文化の黄金期」と称されています。
特に、江戸の都市文化の中心であった京都や江戸では、精緻な染色や織りの職人技が競われ、多彩なデザインが生まれました。粗末な素材や色しか許されなかった庶民も、櫛やかんざしといった小物類で工夫を凝らし、おしゃれを楽しんでいたことが時代劇などからも窺えます。
婚礼用の衣装もこの時代に大きく発展しました。豪華な金糸や銀糸で織り込まれた振袖や、華やかで色鮮やかな色打掛が着用され、花嫁の美しさとともに家族の誇りや社会的地位を示す役割も果たしていました。特に、引き振袖(黒が多い)は結婚後、袖を留めて留袖に仕立て直すという習慣があり、これは現代の持続可能性(SDGs)にも通じる「ものを長く大切に使う」という江戸時代の民衆の知恵が反映されたものでありました。経済的繁栄と社会安定が、着物文化の爛熟をもたらし、多様なデザイン、職人技の発展、そして庶民のおしゃれへの意識向上を促したことは、基本的な生活が安定し、余剰が生まれることで、人々が文化的な表現や美意識の追求にエネルギーを注ぐようになるという普遍的な現象を示していると言えるでしょう。
1.6 明治・大正・昭和時代の洋装化と着物の役割の変化
明治時代以降、西洋文化の導入により、着物の役割は大きく変化しました。明治4年(1871年)には、官吏や軍隊、郵便・鉄道などの仕事服として洋服が採用され、社会に出て働く男性は出勤時に洋装、帰宅時に和装に着替えるという生活スタイルが一般的となりました。和装と洋装が混在する時代となり、袴にブーツを合わせる和洋折衷スタイルが学校教育の場で普及するなど、新しいファッションが生まれた時代でもあります。軍服としても和装が一部使用され、軍人たちは袴に軍帽を合わせた独自のスタイルを取り入れました。
一方で、女性の衣服の洋装化は男性に比べて遅れ、明治初期にはむしろ、伝統的な和装を維持するための公的な規制や洋装の是非に関する議論が存在しました。しかし、髪型に関しては、不便・不潔・不経済とされた日本髪の代わりに、西洋女性の髪型にヒントを得た「束髪(そくはつ)」が明治中期には登場し、女性の髪型は衣服よりも早く洋装化が進みました。
大正時代には、「ハイカラさん」と呼ばれる和洋折衷のファッションが流行し、着物に洋風のアクセサリーを合わせるスタイルが登場しました。浴衣も寝巻きとしてだけでなく、日常着として広く着用されるようになりました。昭和時代に入ると、戦後の高度経済成長とともに洋装が主流となり、和装は結婚式や成人式、祭りなど、特別な場面で着用される衣服へと位置づけられるようになりました。この洋装化の波は、着物が日常生活から徐々に離れ、ハレの日の特別な装いへとその役割を変えていく契機となっていきました。
1.7 現代における着物の位置づけと「モダン着物」の台頭
21世紀に入り、着物は伝統的な美しさを保ちつつも、新たな解釈を加えた「モダン着物」が登場し、若者を中心に再び注目を集めています。現代の着物は、特別な場面での着用が中心であるものの、その美しさと伝統は多くの人々に受け継がれています。
「モダン着物」は、古典柄にはない現代的な柄や色使い、自由な着こなしが特徴です 。派手な色や洋風の色柄が用いられることがあり、レザー小物やハット、レースなど洋服でも用いられる小物を取り入れることで、おしゃれに着こなすことが可能です。例えば、着物の丈を短くアレンジしてスカートやパンツと合わせたり、帯の代わりにベルトを巻いたり、ブーツやスニーカーを合わせたりするなど、従来の着物の常識にとらわれない幅広いコーディネートが楽しめます。このような自由な発想と合わせ方で自分だけのコーディネートを組めることが、モダン着物の大きな魅力となっています。
モダン着物は、個性的でおしゃれな柄・カラーが豊富であること、幅広いコーディネートを楽しめること、着物の街である京都などの旅先へのお出かけ着として使えること、そしておしゃれな普段着として活用できることから人気を集めています。バラ柄、蝶々柄、ストライプ柄、ギンガムチェック柄、市松模様、蛍光・ビビッドカラー、ビタミンカラー、シンプルグレーなど、多様なバリエーションが存在し、個性的なファッションを好む人の、他の人と柄が被りたくないというニーズにも応えています。これにより、着物は単なる伝統衣装としてだけでなく、現代のファッションアイテムとしてもその価値を再発見されつつあります。
第二章:現代の着物の種類と格及びTPO
現代の着物は、その種類、格、そして着用する場面(TPO)によって細かく分類されています。着物の「格」を理解することは、適切な装いを選ぶ上で不可欠であり、帯や小物との組み合わせによっても印象は大きく変化します。
2.1 着物の「格」の基本原則(紋の数、染めと織り)
着物の「格」は、主に紋の数、染めか織りか、そして柄の付け方によって決定されます。
- 紋(もん)の数と種類:
- 五つ紋: 最も格が高く、正式な礼装に使用されます。背中、両後ろ袖、両胸に一つずつ紋が入ります。黒留袖などの第一礼装では、紋の中を白く丸く抜いた上で紋の絵(上絵)を描く、「日向紋(陽紋)」という一番格上の紋を付けるのが基本となっています。
- 三つ紋: 略礼装に適した格式。親族以外の結婚式や正式な慶びの式典などに使用されます。
- 一つ紋: フォーマル寄りの着物として使用可能。パーティや子供の入学式・卒業式など、幅広いシーンで準礼装として着用出来ます。
- 無紋(紋なし): 格式的には、カジュアル着として扱われます。
- 染めと織りの着物の格:
- 染め(後染め)の着物: 白生地に後から染めや柄付けを施したもので、留袖、振袖、訪問着といったフォーマルな装いのほとんどがこれに該当します。一般的に、織りの着物よりも格が高いとされています。フォーマルな装いの物は美しい色とりどりの華やかな柄が特徴となりますが、染めだけで柄がない色無地や、柄があっても控えめな小紋柄の着物もあります。
- 織り(先染め)の着物: 糸を先に染めてから織り上げたもので、紬などが代表的です。普段着や街着として用いられることが多く、染めの着物よりも格は低いとされています。ただし、結城紬や大島紬など、値段的に高級品として知られる織りの着物も存在しますが、どんなに値段が高くてもこれらはあくまで街着であり、冠婚葬祭などのフォーマルな場には不向きとされています。
2.2 第一礼装:黒留袖、色留袖、振袖
第一礼装は、最も格式の高い着物であり、冠婚葬祭、特に慶事において着用されます。
- 黒留袖(くろとめそで):
- 既婚女性の第一礼装であり、五つ紋が入ります。
- 地模様のない黒地のちりめん素材で、上半身は無地、裾に絵羽模様(縫い目を超えて続く一枚の絵のような柄)が施されているのが特徴です。
- 主に結婚式で新郎新婦の母親や近しい親族、仲人夫人が着用します。帯は錦織や唐織の袋帯か丸帯を合わせるのが基本となっています。
- 色留袖(いろとめそで):
- 生地が黒色以外の留袖で、未婚・既婚を問わず着用できます。
- 紋の数によって格が異なり、五つ紋を入れると黒留袖と同格の第一礼装となり、三つ紋や一つ紋は、準礼装として扱われます。
- 上半身は無地で、裾のみに絵柄が広がっている点が特徴となります。主に結婚式(親族)、パーティー、式典などで着用される着物です。
- 振袖(ふりそで):
- 未婚女性の第一礼装であり、他の着物と比べて長い袖丈が特徴となります。
- 袖の長さによって大振袖(約114cm、結婚式・披露宴)、中振袖(約100cm、成人式・友人の結婚式)、小振袖(約85cm、お茶会・パーティ・卒業式)の3種類に分類されます。
- 豪華で色鮮やかな柄が全体に施され、成人式や結婚式(ゲスト)、結納、お見合い、初詣、パーティーなど特別なセレモニーで着用される着物です。
2.3 準礼装:訪問着、付け下げ、色無地、江戸小紋
準礼装は、礼装に次ぐ格の高さを持つ着物で、フォーマルな場で幅広く着用されます。
- 訪問着(ほうもんぎ):
- 振袖や留袖の次に格が高い着物で、未婚・既婚を問わず着用できます。
- 柄が衿・肩・胸・袖などに縫い目をまたがって描かれ、一枚の絵画のように繋がっている「絵羽模様」が特徴です。
- 結婚式、披露宴、七五三、入学式・卒業式などの式典、パーティー、お茶会、観劇など、幅広いシーンで着用可能な着物で、格の高い袋帯を合わせるのが一般的です。
- 付け下げ(つけさげ):
- 訪問着の次に格が高い着物で、訪問着に似ているが、訪問着よりも柄が少なめで、柄の連続性がない場合が多い。
- 柄は控えめであり、ちょっとしたパーティーや観劇など、略礼装として着用される着物です。
- 色無地(いろむじ):
- 白生地を黒色以外の一色のみで染めた無地の着物です。
- 紋の数によって格が変わり、紋付きの色無地は略礼装として、子供の卒業式・入学式、七五三、お宮参りなどに着用出来ますが、紋なしの場合はおしゃれ着として、お食事会や観劇などに用いられます。寒色系の色無地に黒共帯を合わせれば、通夜・法事など半喪の装いにもなります。
- 江戸小紋(えどこもん):
- 生地全体に柄が入っている小紋の一種ですが、無地に見えるほどきめ細かい柄が特徴です。
- 最も格が高い染め技法の三役「鮫」「行儀」「通し」であれば、紋付きとして略礼装に扱われる。お茶会や卒業式などにも着用可能です。
2.4 普段着・おしゃれ着:小紋、紬、浴衣、木綿・ポリエステル着物
普段着やおしゃれ着は、よりカジュアルな場面で気軽に着用される着物である。
- 小紋(こもん):
- 生地全体に柄が繰り返されている型染めの着物で、付け下げや色無地よりも格が低いとされています。
- 街歩き、食事、観劇など、おしゃれ着として幅広く楽しめる着物で、名古屋帯や半幅帯を合わせるのが一般的です。
- 紬(つむぎ):
- 主に先染めの糸で織られた着物で、大島紬や結城紬など、全国にその産地があります。
- 普段着として旅行、散策、カジュアルなイベントなどに適しているとされ、高級品として知られるものもあるが、あくまで街着として扱われる着物です。
- 浴衣(ゆかた):
- 主に夏祭や花火大会、夏のイベントなどで着用する、着物とほぼ同じ形をしたカジュアルな衣類ですが、あくまで浴衣は浴衣であり、着物とは異なります。
- 起源は入浴時に着ていた「湯帷子(ゆかたびら)」とされ、後に夏のくつろぎ着として普及しました。
- 素材は木綿が基本で、絹の着物とは異なり、フォーマルなシーンには着用できません。半幅帯や兵児帯を合わせます。
- 木綿着物・ポリエステル・ウール:
- 日常のおしゃれ着として気軽に着用できる素材の着物です。ポリエステル素材は自宅で水洗いの洗濯が出来るなど、お手入れのしやすさも魅力となっています。
2.5 帯の種類と格
帯は着物の印象を大きく左右する重要な要素であり、着物と同様に格がある。
- 丸帯(まるおび):
- 幅約32cm、長さ約4m48cmで仕立てられ、帯の中で最も幅が広く、重厚な帯です。
- 江戸時代に考案され、最も格式の高い帯とされてきましたが、近年では婚礼衣装や舞妓の衣装に合わせるイメージが強い。裏面にも柄が入っており、結び方にかかわらず柄を楽しめる。
- 袋帯(ふくろおび):
- 幅約31cm、長さ約4m48cmで仕立てられる。
- 振袖や留袖などの第一礼装に合わせても問題のない格式の高い帯となります。喜びを重ねる二重太鼓を結べるため、礼装として格が高い。
- 華やかな色柄はフォーマルシーンに、控えめな色柄は訪問着や付け下げ、色無地などにも合わせられる。小紋や紬にも合わせられる「しゃれ袋帯」も存在します。
- 名古屋帯(なごやおび):
- 幅約31cm、長さ約3m80cmに仕立てられ、袋帯や丸帯と比較して短く、一重太鼓が主流です。
- カジュアルシーンに多く用いられるが、種類によってはセミフォーマルにも合わせられる。華やかな色柄の名古屋帯は、略礼装に合わせて問題ないとされています。
- 半幅帯(はんはばおび):
- 帯幅が細く締め付け感が少ないため、初心者でも簡単に結べ、街着に最適な帯です。
- 結婚式や七五三など畏まった場には不向きですが、普段のファッションとして、柄選びも帯結びも自由に楽しめる。小紋や紬、浴衣との相性が良い。
- 兵児帯(へこおび):
- 最も格の低い帯とされ、フォーマルな着物には使えません。主に浴衣やカジュアルな普段着に用いられます。
着物と帯は格を合わせることが基本であり、例えば黒留袖や色留袖には袋帯、振袖には袋帯、訪問着には袋帯もしくは名古屋帯、小紋や紬には名古屋帯や半幅帯、浴衣には半幅帯や兵児帯が適切とされています。
2.6 小物(帯締め、帯揚げ、草履、バッグ、髪飾り、長襦袢など)の役割とTPO
着物姿は、帯締め、帯揚げ、草履、バッグ、髪飾りといった小物によって印象が大きく変化し、TPOに合わせた選択が重要となります。
- 帯締め・帯揚げ:
- 帯締めは帯を固定する役割があり、帯揚げは帯枕を包み、帯の上部を整える役割を持ちます。
- フォーマルな場では格の高い帯を、カジュアルな場では遊び心のある帯を選ぶことで、コーディネートの幅が広がります。帯締めや帯揚げの色を変えるだけで、同じ着物でも異なる印象を与えることが出来ます。
- 婚礼衣装の帯締めは太く、ふっくらとした丸くげが一般的で、「永遠に続く幸せ」を意味し、決してほどけない二人の絆を表すとされています。
- 草履・バッグ:
- 草履は着物の格式やシーンに合わせて選ぶことが重要です。正装であれば色無地やシックなデザイン、カジュアルな着こなしであれば柄物やポップなカラーリングが適しているとされています。
- 普段使いの着物では、草履や下駄だけでなく、スニーカーやブーツを合わせることもあり、より気軽に楽しめます。特にレザーのショートブーツは、大正時代から用いられており、モダンな着物コーデの定番アイテムとされています。
- 髪飾り・アクセサリー:
- かんざしには鶴や亀、松などの縁起の良いモチーフが用いられ、長寿や幸運を願う意味が込められることがあります 。
- 現代風の着こなしでは、カチューシャやベレー帽など普段と変わらないヘアアレンジを取り入れたり、ピアス、イヤリング、ネックレス、ブレスレットなどのパールアクセサリーや金属アクセサリーを合わせたりすることで、エレガンスや個性を演出できる。ブローチなどを帯飾りの代用として使うことも可能である。
- レースネックインナーやレース手袋、レースバッグ、レース扇子、レースかんざしなどのレース小物は、モダン着物と相性が良いとされる。
- 長襦袢:
- 礼装の際は、白襦袢が基本であり、準礼装では淡い色襦袢も許容される。礼装の格が高いほど白、カジュアルなほど色や柄が濃いものが選ばれます。
2.7 着物の種類と格、主な着用シーン一覧
着物の種類 格 主な着用シーン 備考 黒留袖 第一礼装(五つ紋) 結婚式(親族)、格式高い式典 既婚女性の最高礼装 色留袖 第一礼装(五つ紋)
準礼装(三つ紋・一つ紋)結婚式、パーティー、式典、祝賀会 未婚・既婚問わず着用可能 振袖 第一礼装(未婚女性) 成人式、結婚式(ゲスト)、結納、お見合い、初詣、パーティー 袖丈により大・中・小に分類 訪問着 準礼装 結婚式、パーティー、お茶会、入学式・卒業式、七五三、観劇 未婚・既婚問わず着用可能 付け下げ 略礼装 ちょっとしたパーティー、観劇 訪問着より控えめな柄付け 色無地(紋付き) 略礼装 お茶会、卒業式、入学式、七五三、お宮参り、略式の式典 紋の数で格が変わる 江戸小紋(紋付き) 略礼装 お茶会、卒業式、略式の式典 無地に見えるほど細かい柄が特徴 小紋 おしゃれ着 街歩き、食事、観劇 全体に柄が繰り返される 紬 普段着 旅行、散策、カジュアルなイベント 先染めの糸で織られる 木綿着物・ポリエステル・ウール 普段着 日常のおしゃれ 気軽に着用できる 浴衣 普段着 夏祭り、花火大会、カジュアルなイベント 夏のカジュアル着、木綿素材が基本 第三章:着物業界の現在の状況及び斜陽産業になった要因
着物業界は、長年にわたり市場規模の縮小という課題に直面しており、「斜陽産業」と称されることも少なくありません。その背景には、消費者のライフスタイルの変化、業界特有の商慣行、そして着物そのものに対する認識の変化など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
3.1 呉服小売市場規模の推移と現状
呉服小売市場は、ピーク時の7分の1にまで縮小していると分析されています。2021年の呉服小売市場規模は小売金額ベースで前年比12%減の2,446億円と推定され、2020年の大幅な落ち込みからの回復が見られました。2022年、2023年もプラスで推移しているが、2023年の市場規模は2,240億円(前年比101.4%)と推計されており、2024年には微減の2,230億円(前年比99.6%)が予測されています。
この市場の縮小は、戦後の洋装化により着物需要が減少したことが主な原因と考えられています。特に、お宮参り、七五三、入学式、卒業式、成人式、結婚式など、着物を着用する人生の節目のイベントが新型コロナウイルス感染症による自粛に伴い、厳しい状況が続いていました。しかし、2023年に「5類」に移行したことにより、人の集まる機会が増え、着物の着用機会も増えつつあります。
販売チャネル別では、ネット通販の割合が年々増加しており、令和5年では平成19年比で21.5%増となっています。専門店は底堅く推移しているものの、百貨店や催事・訪問販売は厳しい状況が続いています。レンタル市場は規模は縮小しているものの、着物市場全体の割合では2割前後を維持しています。
呉服小売市場規模の推移
年 市場規模(億円) 前年比 2020 - 大幅減 2021 2,110 109.6% 2022 - プラス推移 2023 2,240 101.4% 2024(予測) 2,230 99.6% 2020年、2022年の具体的な数値は提示されていないため、傾向を記載。
3.2 「着物離れ」の主要因
着物業界が「斜陽産業」と呼ばれる主な要因は、消費者の「着物離れ」にあります。これは複数の複合的な要因によって引き起こされています。
3.2.1 着付けの難しさ、時間、動きにくさ
最も大きな要因の一つは、着付けの難しさ・煩雑さによる敷居の高さです。多くの人が「着付けの仕方がわからない」ことを理由に普段着物を着ないと回答しており、その割合は50.1%に上ります。また、「着付けに時間がかかる」(37.3%)や「身体を動かしにくい」(33.5%)といった、着物着用に伴う不便さも着物離れの原因として挙げられています。現代の洋服の利便性や手軽さに慣れてしまった人々にとって、着物の着方や脱ぎ着の煩雑さ、着用時の窮屈さは大きな障壁となっていいます。特に、30代や40代で「着物を着たことがない」と回答する割合が約40%に達していることは、親世代が着物を着る機会が少ないため、子供世代の着用機会がさらに減少する可能性を示唆しています。
3.2.2 高価格帯と手入れの煩雑さ
着物の高価格帯も、購入をためらわせる大きな要因と考えられています。特に正絹の着物や高級紬、有名作家の作品などは高価であり、一般の消費者にとっては手が出しにくい価格設定となっている。また、着物の手入れの煩雑さも課題と考えられています。着物は、着用後の陰干し、正しい畳み方、たとう紙での保管、湿気の少ない暗所での温度・湿度管理(15~25℃、湿度50~60%)、防虫剤の使用、そして数ヶ月に一度の虫干しなど、洋服に比べて専門的な知識と手間が必要とされます。汚れが付着した際のシミ抜きや修理も専門業者に依頼する必要があり、これにはクリーニングや修理のコストがかかります。これらの維持コストや手間が、着物の購入・着用を敬遠させる要因の一因となっています。
3.2.3 専門知識の不足と情報の不透明性
着物に関する専門知識の不足は、消費者と業界双方に不信感を生み出しています。消費者は着物の格、種類、TPO、そして適正価格に関する情報が不透明であると感じており、これが購入への心理的障壁となっています。特に、買取業者の中には専門知識が不足していたり、査定基準が不透明であったりするケースがあり、本来の価値よりも大幅に安い査定額を提示されることが多々あります。このような不透明な価格設定や不適切な販売手法は、消費者からの不信感を醸成し、着物離れを一層進めるリスクがあると言えるでしょう。
3.2.4 着用機会の減少(冠婚葬祭イベントの自粛など)
着物が「ハレの日」の特別な装いとして位置づけられるようになった現代において、冠婚葬祭などのイベントの減少は、着物の着用機会の直接的な減少につながります 。特に新型コロナウイルスの流行期には、入学式や成人式、結婚式といったイベントが自粛されたことで、着物の需要が急激に減少しました。これにより、着物市場は大きな打撃を受け、市場規模の縮小が加速した側面があります。
3.3 業界構造と商慣行の課題
着物産業は長い歴史を持つがゆえに、過去から続く事業者間の商慣行に課題が存在します。
- 不透明な価格設定と不適切な販売手法: 消費者視点で見ると、不透明な価格設定や不十分な表示、不適切な販売手法が「着物離れ」の要因となる場合があります。例えば、「はれのひ」事件のように、成人式当日に業者が突然営業を停止するといった事案は、業界全体に対する不信感を招きかねません。
- 委託販売や長期手形などの事業者間課題: 事業者間においては、委託販売や長期の手形、歩引きといった商慣行が課題として挙げられています。これらの慣行は、着物の作り手に対してリスクがしわ寄せされることで、生産体制が崩れる可能性や、卸や小売事業者の目利きの低下により、市場に優れた商品が流通しなくなるリスクをはらんでいます。
3.4 レンタル市場の台頭と購入需要の減少
近年、着物を購入せずにレンタルで済ませる人が増加しており、一人当たりの消費額が大幅に減少している。これは、着付けの難しさや高価格といった購入障壁が高い一方で、レンタルであれば手軽に利用できるという利便性が評価されているためと考えられています。レンタル市場の成長は、着物の着用機会を維持する一方で、新品着物の購入需要をさらに減少させる要因となっており、特に、一度だけの着用であればレンタル着物店が安価であるという認識が広まっている。
3.5 後継者問題と人材不足
市場の縮小が続く着物業界では、後継者問題や人手不足も深刻な課題です。着物レンタル店においても、接客や着付けには専門的な知識や技術が必要とされるため、経験豊富なスタッフや着付け師の確保と育成が課題となっています。これらの問題は、伝統産業としての着物業界全体の持続可能性を脅かす要因となっていますが、業界内ではM&Aが活発に行われるなど、業界再編の動きも見られています。
第四章:伝統文化である着物を未来につなぐために必要なこと
日本の伝統文化である着物を未来へつなぐためには、現在の課題を克服し、現代のライフスタイルや価値観に合わせた多角的なアプローチが必要です。
4.1 「着物離れ」を克服するためのアプローチ
着物離れの根本原因である「着付け・着方」の難しさや、価格、手入れの煩雑さを解消することが、着物文化を普及させる上で最も重要です。
- 着付けの簡略化と普及教育:
- 「着付けの仕方がわからない」という障壁を取り除くため、無料の着付け教室や、簡単でシンプルな着付けプログラムの提供が有効です。着物や小物のレンタルを含め、気軽にきものに親しめる機会を増やすことが重要であるが、着付け教室は評判が様々なので、事前に良く調べる必要があります。
- 学校教育での着装教育や製作講習、指導者の育成を通じて、着物に関する専門的知識や着装技術を持つ人材を増やすことも不可欠です。
- 価格の適正化と多様な選択肢:
- 「価格が安い」ことが着物を着る理由の一つとして挙げられているように、手頃な価格帯の着物を提供することが重要です。
- レンタル市場の活用は、購入のハードルを下げる有効な手段です。また、リサイクル着物店の活用は、手軽に着物を始める入り口として非常に魅力的であり、一式揃えることで結果的に安価に楽しめるという利点があります。
- 不要になった着物を新たな衣服や小物に作り替える「アップサイクル」は、着物に新たな価値を生み出し、伝統文化の継承や環境負荷の軽減に貢献します。パーティードレスやワンピース、シャツ、チュニックなど、現代の洋服としてリメイクするサービスは、着物を持たない層にもアプローチできます。
- 手入れの簡便化と情報提供:
- 着物の手入れの煩雑さを解消するため、自宅で手軽に洗える素材の開発(例:ポリエステル素材の着物)や、手入れ方法に関する分かりやすい情報提供が求められています。
- 専門のクリーニングや修理サービスをもっと一般的なサービスになるように、情報発信などでさらなる認知度を高めることで、より利用しやすくすることも重要です。
4.2 現代のライフスタイルに合わせた着物の提案
着物が現代のライフスタイルに溶け込むためには、デザインや素材の革新、そして自由な着こなしの提案が不可欠です。
- 「モダン着物」の推進とデザイン・素材の革新:
- 個性的な色柄や洋風小物を取り入れた「モダン着物」は、着物の常識にとらわれない自由な着こなしを可能にし、若者を中心に人気を集めています。バラ柄、蝶々柄、ストライプ柄、ギンガムチェック柄など、現代的な柄や蛍光・ビビッドカラー、ビタミンカラーなど、多様なデザインを展開することが重要です。
- 新素材の開発も進められています。例えば、自然な風合いと環境に優しい特性を持つ「野蚕糸(やさんし)」は、耐久性や通気性に優れ、ミニマルなデザインやエシカルファッションとの融合に適しています。野蚕糸を他の天然繊維や合成繊維と混ぜ合わせる混紡技術や、染色技術の向上により、デザインの幅が広がっています。また、東レが開発した植物由来PETと複合紡糸技術を融合した新素材「シルック美來™」のような、サステナブルな素材も注目されています。
- 洋装小物との融合と自由なコーディネート:
- 着物の裾を短めに着付けて足元をすっきりさせ、ブーツやスニーカーを合わせる、帯の代わりにベルトを巻く、レースやファーなどの洋風小物を取り入れるなど、洋服感覚で楽しめるコーディネートを提案する。
- カチューシャ、ベレー帽、パールアクセサリー、ブローチなど、普段使いのアクセサリーやヘアアレンジを取り入れることで、着物コーデに統一感と個性を加えることが出来ます。
4.3 デジタル技術の活用(DX)
着物業界のDX推進は、市場の縮小という課題に対する重要な解決策の一つです。
- 顧客カルテのデジタル化とデータ活用:
- 販売員の記憶や手書きの手帳に頼りがちだった顧客情報をデータベースとして構築し、社員がタブレットで使える顧客カルテを作成することで、顧客情報を会社全体で共有・蓄積できる。これにより、顧客の嗜好や購買履歴に基づいたパーソナライズされたサービス提供が可能となります。
- LINEを活用したデジタルマーケティング:
- 顧客とのコミュニケーションツールとしてLINE公式アカウントを活用し、顧客の嗜好に合った商品やイベント情報を発信する。販売員個人のLINEでのやり取りを会社公式アカウントに移行することで、履歴共有や引き継ぎの効率化が図れます。
- デジタルクローゼットアプリの開発:
- 顧客が所有する着物、帯、小物をスマートフォン上で管理できる「デジタルクローゼット」アプリの開発は、顧客の利便性を大幅に向上させる 。さらに、シーズンオフの和服を預かり、丸洗いして保管するサービスと連携させることで、着物の手入れの煩雑さという課題にも対応できます 。これらのデジタルツールで蓄積されたデータを活用し、次のアクションにつなげることが、DXの真の目的です。
4.4 国内外への「きもの」文化の発信とプロモーション
着物文化を未来へつなぐためには、国内だけでなく、海外への積極的な発信とプロモーションが不可欠です。
- インバウンド観光客向け体験プログラムの拡充:
- 着物レンタルと街歩き、着付け体験と茶道、舞妓体験、季節のイベントとのコラボレーションなど、外国人観光客に人気の高い着物体験メニューを拡充する。これにより、日本の伝統と美しさを直接体験してもらい、地域経済の活性化にも寄与できると考えらます。
- オンライン予約システムや多言語対応のウェブサイト、現地メディアとの連携、レビューサイトの活用など、外国人観光客がアクセスしやすい情報提供とプロモーション体制を強化することが必要です。
- SNSを活用した情報発信とブランディング:
- InstagramやYouTubeなど、視覚に訴えるSNSは着物や振袖のデザイン、コーディネートの魅力を伝える上で非常に効果的です。おしゃれな投稿や動画を通じて、着物の楽しさや多様な着こなし方を国内外に発信し、若い世代への訴求力を高めることが重要。
- 顧客目線で、小物までセットで魅せる写真や、ヘアスタイルまで含めたトータルコーディネートを掲載することで、顧客の満足度を高め、来店や購入に繋げることができます。
- 海外セレブとのコラボレーション事例:
- ミランダ・カー、デュア・リパ、レディー・ガガ、キム・カーダシアン、セレーナ・ゴメスなど、多くの海外セレブが来日時に和装を披露しており、その姿は世界中で注目を集めています。これらの事例は、着物が国際的なファッションアイテムとしての可能性を秘めていることを示唆しており、今後もこのような影響力のある人物とのコラボレーションを通じて、着物の魅力を世界に発信していくことが期待されます。
4.5 持続可能な産業構造への転換
着物産業が持続的に発展していくためには、新たな価値創造と産業基盤の強化が不可欠です。
- アップサイクルによる新たな価値創造:
- 不要になった着物を解いて、現代的な衣服や小物(バッグ、アクセサリーなど)に作り替えるアップサイクルは、世界に一つだけのオリジナル作品を生み出すだけでなく、持続可能なファッションの選択肢を広げ、伝統文化を次世代に伝える新しい方法として注目されています。これにより、環境への負担を減らしつつ、文化的価値の再発見にも繋がります。
- 伝統技術の継承と職人育成:
- 着物の生産には、染色や刺繍など高度な加工技術が必要であり、これらの技術を維持・継承することが重要です。着物を着る人が増えれば、仕立てをする人、反物を織る人、それを染める人といった、着物に関わる人たちの産業も守ることができます。職人の技術による着物の修復は、着物を長く大切に使う上で欠かせない要素であり、着物の価値を高め、次世代にも受け継いでいくことに繋がります。
- 地域振興との連携:
- 着物を活用した地域振興を推進することで、着物産業全体の活性化を図ることができます。地域の観光施設やホテルとの提携、旅行代理店とのコラボレーションを通じて、着物体験を含むパッケージツアーを提供することは、より多くの観光客を引きつけ、地域経済にも貢献します。
最後に
着物文化は、日本の歴史と美意識が凝縮された貴重な伝統でありながら、現代においては「着物離れ」という深刻な課題に直面しています。市場規模の縮小は、着付けの難しさ、高価格、手入れの煩雑さ、着用機会の減少、そして業界内の不透明な商慣行といった複合的な要因によって引き起こされています。しかし、これらの課題は、着物文化を未来へつなぐための変革の機会でもあります。
着物文化の持続的な発展のためには、消費者中心のアプローチが不可欠です。着付けの簡略化と普及教育を通じて、着物をより身近なものとし、レンタルやリサイクル、アップサイクルといった多様な選択肢を提供することで、購入のハードルを下げる必要があります。さらに、現代のライフスタイルに合わせた「モダン着物」の推進や、野蚕糸や植物由来素材といった新素材の開発は、着物の新たな魅力を創出し、若い世代への訴求力を高めます。
デジタル技術の活用は、顧客情報の管理、マーケティング、そして顧客サービスの向上において、業界の効率化と顧客体験の向上に大きく貢献する。デジタルカルテやLINEを活用したコミュニケーション、デジタルクローゼットアプリの開発は、着物業界が「モノを売る会社」から「デジタルを活用した体験を提供する会社」へと転換するための重要なステップとなります。
国内外への積極的な文化発信も欠かせません。インバウンド観光客向けの体験プログラムの拡充や、SNSを活用したブランディング、海外セレブとのコラボレーションは、着物の国際的な認知度を高め、新たな需要を喚起することが重要になります。
最終的に、着物産業が持続可能な形で発展するためには、アップサイクルによる新たな価値創造、伝統技術の継承と職人育成、そして地域振興との連携を通じて、産業構造全体を強化していく必要があります。これらの多角的な取り組みが連携することで、着物は単なる伝統衣装に留まらず、現代のファッション、文化、そして持続可能な社会の象徴として、未来へと受け継がれていくことでしょう。
本物の染み抜き専門店に相談
ご相談は無料です。お気軽にご相談ください!